こんにちは。「gusare」編集部です。
教育実習の本番で、意外と悩んでしまうのが「最後の挨拶」です。
最後の挨拶は実際に教育実習を経験しないと準備することも難しいですし、どのような内容を言うと良いのか悩んでしまいがちです。
今回の記事では、実際に教育実習を行った経験を元に、実践で使えるような教育実習での最後の挨拶を例文付きで解説させていただきます。
【教員志望にもオススメ!効率よく企業からのスカウトが届く就活サービス!】
・Lognavi(ログナビ)
学生限定のSNSコミュニティ。相性のいい企業からスカウトが届く!
・アカリク
理系学生・大学院生に特化した就活サイト。研究内容でスカウトが来る!
教育実習で最後の挨拶に悩む……!
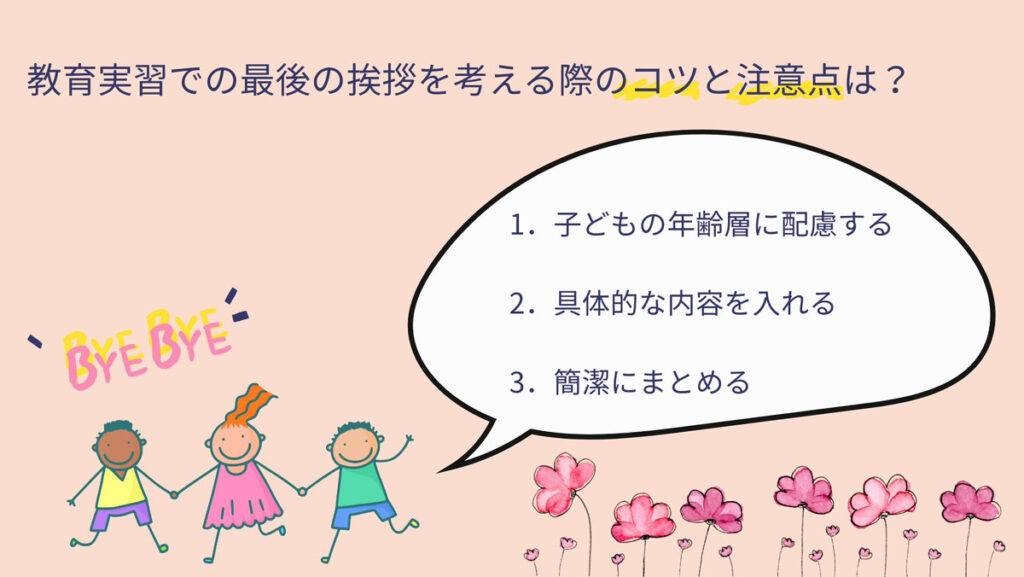
始まる前は長く感じる教育実習の期間ですが、いざ始まってしまうとあっという間に終盤を迎えることになります。
大変だったことも含めて、「振り返ってみれば良い経験だったな」と感じる方も多いのではないでしょうか。
教育実習の最終日には実習生からの挨拶の時間が設けられている場合がほとんどです。
これまで関わってきた子どもたちに向けての挨拶ですが、「何を話したらいいかわからない」と頭を抱えてしまう教育実習生も多くいます。
私自身も教育実習を経験した身ですが、最終日を前にして他の実習生たちと集まって「最後の挨拶、何を話す?」と相談した覚えがあります。
濃密な実習期間を総括する言葉ですから、悩んでしまうのも当然と言えるかもしれません。
今回の記事では「教育実習の最後の挨拶が思いつかない!」「最後の挨拶を考えるコツってあるの?」とお悩みの方に向けて、教育実習での最後の挨拶を考える際のコツと注意点について解説します。
実際に使える例文もご紹介しますので、教育実習の最後の挨拶を考える際にはぜひ参考にしてみてください。
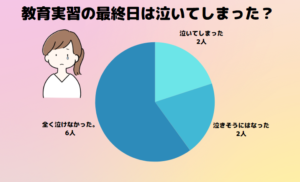
教育実習での最後の挨拶を考える際のコツと注意点
教育実習における最後の挨拶は、実習期間中に配属されていたクラスの子どもたちに向けてのものとなります。
ここで重要なのは、実習生という自分の立場が子どもたちにとってどんなものであるかを念頭に置いて考えることです。
実習生とはいえ、子どもたちにとってはひとりの先生です。実習期間中、多くの実習生がその責任を感じて実習に臨んでいるでしょう。最後の挨拶を考える時もその視点を忘れてはいけません。
一方で、実習生は子どもたちから学ぶ立場でもあります。
子どもたちにその自覚はないことが多いですが、彼らの貴重な時間を実習生の学びのために充ててくれたのは事実です。
最後の挨拶を考える際にも、子どもたちへの感謝と謙虚さを持つべきです。
子どもたちにとっての実習生の立場をきちんと踏まえた上で、教育実習での最後の挨拶を考える際のコツを3つご紹介します。
子どもの年齢層に配慮する
教育実習の最後の挨拶を考える時に一番重要なことは、受け取り手となる子どもたちの年齢層に配慮することです。
実習先が小学校と高校では、当然最後の挨拶も変わってきます。
さらに言えば小学1年生に向けた挨拶と小学6年生に向けた挨拶も違ってくるはずです。
実習期間中に関わってきた子どもたちの年齢を考慮し、その年齢の子どもたちに伝わりやすい言葉や内容にするのがベストです。
具体的な内容を入れる
教育実習の最後の挨拶を考える際の2つ目のコツは、具体的な内容を入れることです。
具体的な内容をひとつ盛り込んだ挨拶にすることで、子どもたちにこの実習期間で得たものを伝えることができます。
学んだことや嬉しかったことなど、教育実習期間で得たプラスな感情を伴うものを選びます。
たとえば「休み時間に一緒に鬼ごっこをしたのが楽しかった」「自分が受け持った授業でたくさん発言してくれて嬉しかった」など、子どもたちがいなければ感じることができなかったことを盛り込むと良いでしょう。
実習期間中のエピソードのほかにも、この実習を通して将来的にどんなことをしていきたいかを話すのも具体的な内容のひとつです。
特に進路選択を控えた中学生や高校生にとって、実習生は少し先の未来を歩く先輩でもあります。実習で得た経験や学びをどのように活かしていくかを話すことは、子どもたちにとっても何かのヒントになるかもしれません。
できるだけ簡潔にまとめる
教育実習の最後の挨拶を考える際の3つ目のコツは、できるだけ簡潔にまとめることです。
2つ目のコツで解説した“具体的な内容を入れる”ことを意識すると、あれもこれも言いたくなって挨拶が長くなってしまうことがあります。
しかし長すぎる挨拶は子どもの集中力を削ぎますし、自分の他にも挨拶をする実習生がいるケースもあります。
そのため、最後の挨拶はできるだけ簡潔に、短くまとめるのがベターです。
目安としては、時間にして1分、文章にして3〜5文くらいをおすすめします。
少し短く感じるかもしれませんが、実際に挨拶をするときは聞き取りやすさを考慮してゆっくり話すことが大切です。そのため、だいたい3〜5文くらいの挨拶だとちょうどよい長さに収めることができます。
実践で使える!教育実習の最後の挨拶の例文3選!
ここまで教育実習の最後の挨拶を考える際のコツを3つ解説してきました。
なんとなく自分で挨拶を考えるヒントのようなものが掴めてきたのではないでしょうか。
ここからは実践で使える教育実習の最後の挨拶の例文を、実習先の学年別に3つご紹介します。
小学校低学年向けの挨拶
「教育実習生の◯◯です。みんなとたくさんお話をしたり、休み時間に一緒に遊んだりできたことがとても楽しかったです。また運動会や発表会の時にみんなの頑張る姿を見に来るので、その時は「◯◯先生!」とお話ししにきてくれたら嬉しいです。今日まで3週間、ありがとうございました。」
小学校低学年の子どもたちに挨拶するときは、少し砕けた口調でも構いません。
内容も子どもたちと感情を共有できそうなものを選び、最後まで親しみやすい先生でいることを心がけましょう。
この年齢の子どもたちの場合、実習最終日に色紙やメダルをプレゼントしてくれることがあります。
挨拶の前に渡された場合は、そのプレゼントへのお礼も一緒に伝えるとよいでしょう。
小学校高学年〜中学生向けの挨拶
「教育実習生の◯◯です。今日でみなさんと過ごすのは最後になります。この3週間、一緒に生き物の観察をしたり勉強をしたりできて楽しかったです。△△学校でのことを忘れずに、素敵な先生になれるようにこれからも頑張ります。短い間でしたがありがとうございました。」
小学校高学年〜中学生向けの挨拶では、授業や学習の内容に触れるのもアイデアのひとつです。
特に実験や観察、自分が担当した授業のことなどは挨拶にも盛り込みやすく、子どもたちの印象にも残っていることが多いのでおすすめです。
また、このくらいの年齢になると実習生の今後に興味がある子どもたちが増えてきます。
自分のこの先のことにも少し触れるとよいでしょう。
中学生〜高校生向けの挨拶
「教育実習生の◯◯です。今日まで3週間、ありがとうございました。日々授業や部活を頑張るみなさんの姿に励まされて、無事に実習を終えることができました。今日までの経験を糧に、大学に戻っても勉強や研究に打ち込んでいこうと思います。勉強することは未来を拓くことでもありますので、みなさんも夢に向かって頑張ってください。応援しています。短い間でしたがありがとうございました。」
中学生〜高校生に向けた挨拶は、少し長めにしてメッセージを盛り込むとよいでしょう。
例文では勉強に焦点を当てていますが、「少しでもやりたいと思ったことには勇気を持って挑戦してみてください」「今のうちにたくさん遊んで、いろんなことを経験してください」のようなものでも構いません。
実習生の経験からのメッセージは、多感な年頃の彼らには響くことがあります。
まとめ
教育実習の最後の挨拶は、実習期間を共に過ごした子どもたちへのメッセージです。
考えれば考えるほど何を言えばいいかわからなくなってしまう人も多いでしょう。
教育実習の最後の挨拶は、子どもたちへのお礼と具体的な実習中のエピソード、そして今後の自分の展望で構成するとまとまった挨拶になります。
関わってきたクラスの子どもたちの年齢にあった内容や話し方を心がけて考えてみましょう。
本記事では教育実習の最後の挨拶を考える際のコツと、実践で使える例文をご紹介しました。
教育実習の最後の挨拶に悩んでいる方ははぜひ参考にしてみてください。
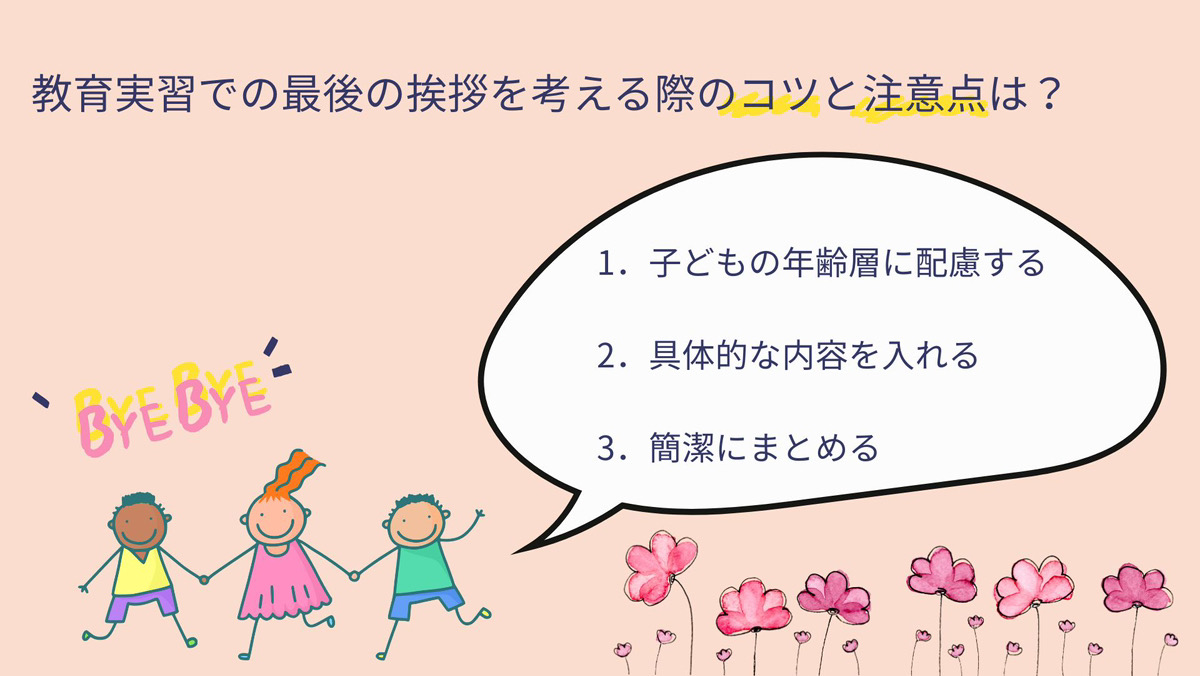

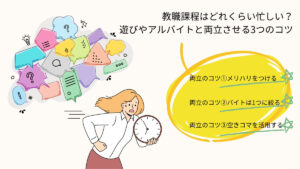
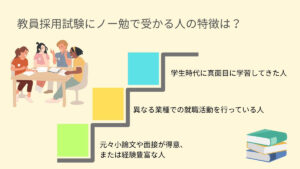
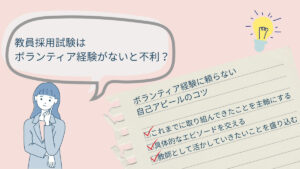

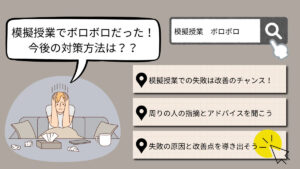
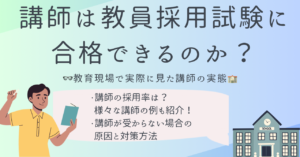

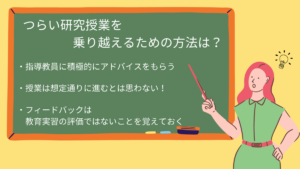




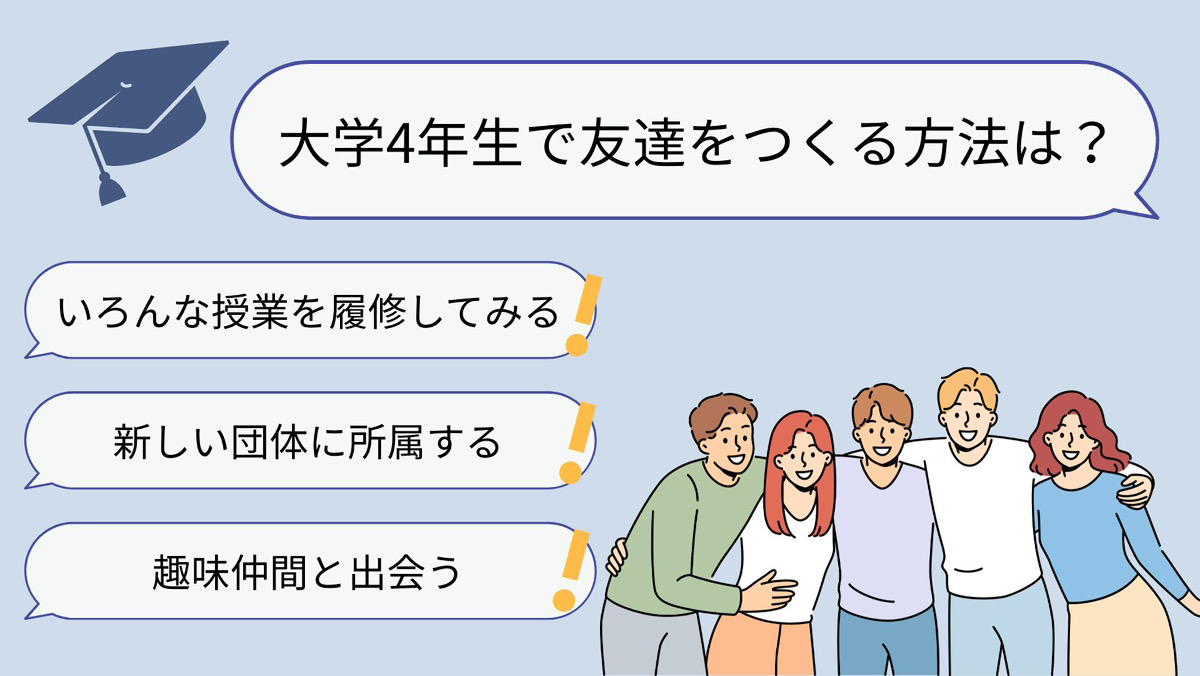
コメント