こんにちは。「gusare」編集部です。
教室長の仕事に興味がある方や、最近教室長になったばかりという方の中には、「塾の教室長の離職率ってどれくらいなんだろう?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかと思います。
今回の記事では、実際に塾の教室長として働いた経験を元に、塾の教室長の離職率はどれくらいなのかについて解説させていただきます。
【20代にオススメな転職サイト・転職エージェント】
マイナビジョブ20’sスカウト:待つだけで企業からスカウトが届く!自分の市場価値を知りたい方にオススメ。
第二新卒エージェントneo:個別面談や書類・面接対策などサポート充実!転職を少しでも考えている方にオススメ。
塾の教室長の離職率ってどれくらいなの?

私は新卒で個別指導塾の教室長候補として採用され、約4カ月の研修後に約2年間教室長として勤めていました。また、在職中は人事として転職者を採用する面接官としての役割も担っていました。
その時の体験を交えながら、「塾の教室長の離職率ってどれくらいなの?」というテーマについて説明していきたいと思います。
実際、私も教室長として勤務していた時、周りの同期や先輩が次々に辞めていくのを見て、「塾の離職率ってどれくらいなんだろう…?」と思ったことがあります。(実際に計算してみたこともあります…笑)
今「そろそろ塾の教室長を辞めたいなぁ・・・。」と感じている方は、↓こちらの記事もぜひ合わせてチェックしてみてください。
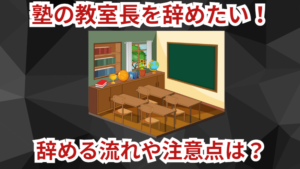
新卒での教室長の離職率
それでは、ここからは新卒採用をされた教室長の離職率がどれくらいなのかについて解説して行きたいと思います。大手就職情報サイトに、過去3年間の新卒定着率が掲載されていたので、そのデータも参考にしていきたいと思います。
数多くある会社の中から、ざっと100社ほど見てみました。
この中には、教室長の募集があり、かつ定着率が記載されていた会社が大体24社ほどありました。(多少誤差はあるかもしれません)
今回はこの24社のデータをもとに、平均的な離職率を割り出してみたいと思います。
(離職者の総数)÷(採用者の総数)×100=(平均離職率)
今回はこの計算式で計算してみます。
これを、データが記載されていた2019年〜2022年度の4年間分出してみることにしました。
年によって記載が無い会社もあるので、データがあるものだけを抽出して計算してみると、
2019年…(3社の離職者の総数)÷(3社の採用者の総数)×100=約36%
2020年…(22社の離職者の総数)÷(22社の採用者の総数)×100=約32%
2021年…(24社の離職者の総数)÷(24社の採用者の総数)×100=約20%
2022年…(21社の離職者の総数)÷(21社の採用者の総数)×100=約16%
このような結果になりました。
大卒の就職後3年離職率は約3割と言われているため、その範囲からは外れていない、もしくは平均よりやや低いことが分かりました。
ただ、このデータは企業の採用ページに載っているものなので、年々離職率が下がっている企業のみがデータを載せていることが考えられます。実際、定着率を載せている企業は他業種に比べると少ない印象でした。そのため、目に見えるデータとしては、年を追うごとに離職率が下がっているように見えるのかもしれません。
中途入社の教室長の離職率
中途入社のみの教室長の離職率はほとんど公表されていませんが、厚生労働省が出している雇用労働調査を見ると、2022年度の「教育、学習支援業」の離職率は15.2%となっています。
ここでの離職率は、
(2022年に「教育、学習支援業」から離職した人数)÷(2022年に「教育、学習支援業」に入職した人数)×100=(離職率)
とされていますので、中途入社の教室長の離職率ともある程度近いデータかと思います。
また、「教育、学習支援業の離職者が前年と比べて22万人ほど減少した」というデータもあったので、実際に離職者は減ってきているのかもしれません。
他業種と比べると、
最も離職率が低いのは「鉱業、採石業、砂利採取業」の6.9%
最も離職率が高いのは「宿泊業、飲食サービス業」が26.8%
ですので、他業種と比べたら中央値、もしくは平均的な数値と言えるのではないでしょうか。
体感ですが、実際学習塾で勤務していると、中途の方の教室長離職率は新卒と比べるとかなり低い気がします。
また、中途採用で教育業界に入る方は、一通りバリバリキャリアを築いて稼いでこられた方が、「多少待遇が悪くても良いからやりがいのある仕事をしたい!」と思って入られることが多いため、定着率は高い印象があります。
もし離職される方がいるとすれば、
「◯年目に辞める方が多い」というよりは、
•病気などの既往歴がある方
•家族の事情で引越しをする方
など
やむを得ない事情で急遽辞められる方が多いかなと思います。
離職率が低い学習塾を選ぶポイントは?
先ほどご説明してきたように、塾業界の離職率はそこまで高くないですが、自分自身は新卒で塾の教室長になって結構大変でした。また、自分の周りの教室長の中には、ワークライフバランス激務で苦しんで離職してしまった人もいました。
そのため、学習塾業界に就職•転職する場合は、業界の中でも離職率が低い会社に就職することを強くおすすめします。
ここからは、離職率が低い学習塾を選ぶポイントを解説していきたいと思います。
就職情報雑誌や就活サイト等で定着率を確認する。
まずは、就職情報雑誌や就活サイト等に定着率が公表されているかを確認しましょう。定着率や離職率が公表されていない場合は、定着率が低いために公表されていないこともあります。
また、掲示板や転職口コミサイトなどを確認することで、どういった理由で社員が退職を決めたのかも調べることもできます。
また、はっきりとした離職率が分からなくても、
•どういった理由で離職したのか
•勤続年数
•どのくらいの年代の方が辞めているのか
が分かれば、大体の離職率や定着率をイメージすることも出来るかもしれません。
給与面だけでなく、福利厚生がしっかりしている会社を選ぶ。
次に、手厚い福利厚生があるかどうかをしっかり確認しましょう。
離職率が高い会社では、月給を引き上げて求職者の興味を惹くこともあります。この理由としては、退職者が多く人が集まりにくいためです。
希望する求人の月給が良かったとしても、すぐには飛び付かず、
•賞与はあるのか
•昇給制度はあるのか
•残業代は出るのか
•休暇は十分にとれるのか
•それ以外の福利厚生はあるのか
などを確認して総合的に判断することをおすすめします。
学習塾事情に詳しい人から情報をもらう。
加えて、学習塾事情に詳しい人に話を聞くことで、現場の声や最新情報を得ることが出来ます。
ネットの情報には、真偽が分からないものや昔の情報も多くあります。そのため、実際に塾業界で働いている人や転職エージェントなどに相談することも、離職率を知る方法として挙げられると思います。
私も塾業界で働いていますが、学習塾間で転職をされている方も多く、「〇〇の塾は最近辞める人が多いらしい」のような情報が入ってくることもあります。
もし周りに塾業界で働いている人がいれば、離職率について聞いてみるのも手だと思います。
逆に、コネクションが無いという方で、今後教室長からの転職を考えておられる方は、一度転職エージェントに相談してみるのもありだと思います。転職エージェントは求人企業の社内環境にも詳しいこともあります。私も転職を考えて転職エージェントに相談した時、内部の様子や勤続年数なども教えていただきました。
同じ業種の中でも、会社によって、またその人によって、働きやすさは異なると思います。
転職のプロに相談し、その会社で自分自身が長く働けるかどうか考えてみると良いかもしれません。

第二新卒エージェントneoは、20代や第二新卒の転職に特化した転職エージェントです。
転職サイトとは違い、個別面談をした上で求人を紹介してくれたり、書類・面接対策などのサポートが充実しているのが特徴です。転職活動の経験が少ない方でも丁寧にサポートをしてくれるのが魅力ですね。転職を少しでも考えている方や、効率よく転職活動をしたい方にはオススメです。

転職エージェントナビは、約300人の転職エージェントの中から自分に合った方を無料でマッチングしてくれるサービスです。
自分の経歴や希望する業界などに合わせて最適な転職エージェントを紹介してくれるため、より親身に自分に合った転職活動をサポートしてくれるのが魅力です。
まとめ
「塾の教室長の離職率ってどれくらいなんだろう?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかと思います。今回検証してみたところ、平均的な離職率であることが分かりましたが、会社によっては離職率が高いところもあります。
しっかり情報を仕入れて、離職率が低く、自分自身が働きやすい会社を選ぶことをおすすめします。
いきなり塾の教室長になって辛いと感じている方は、↓こちらの記事も参考にしてみてください。



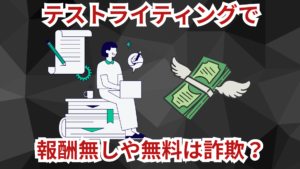
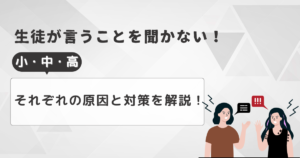
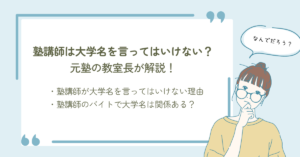
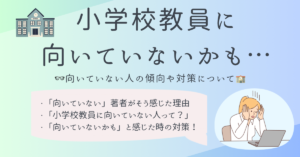

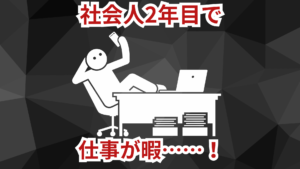





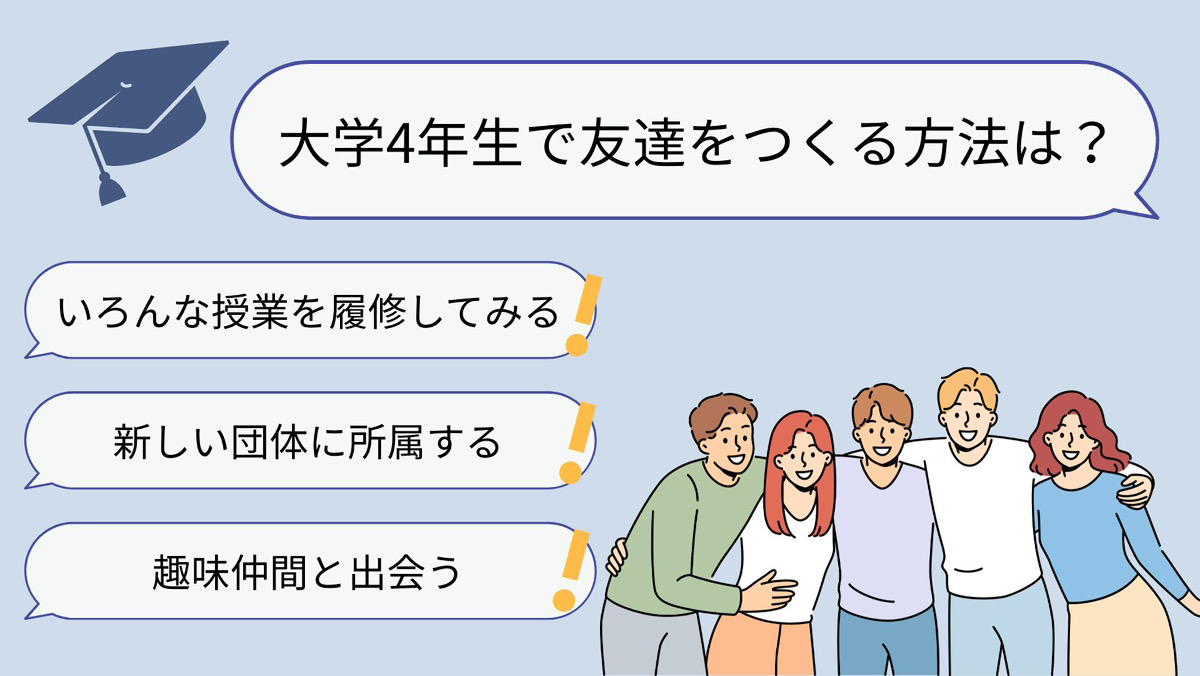
コメント